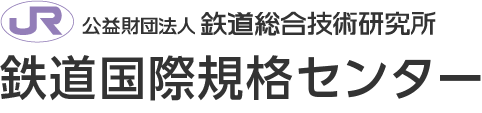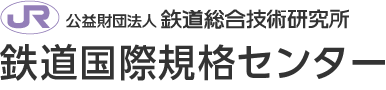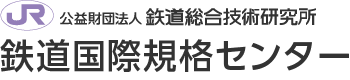鉄道技術標準化調査検討会では、鉄道分野における国際標準化及び国内標準化活動に対して顕著な業績を挙げた者を称え、表彰し、以って受賞者の更なる支援と関係者による標準化活動の重要性認識の増進を目的として、平成19年度より「標準化活動表彰」を実施しています。平成23年度からは、顕著な業績を挙げた方に贈られる「標準化活動貢献者表彰」に加えて、新たに、今後の継続的な活躍を期待する方に贈られる「標準化活動奨励者表彰」を設け、表彰制度を充実させています。
受賞者は以下の通りです。
|
|
|
令和3年度 標準化活動貢献者表彰 受賞者 (50音順)
|
|
| 受賞者 |
所属 |
受賞理由 |
| 髙野 靖 氏 |
国立大学法人京都大学 |
ISO/TC 43(音響)/SC 1(騒音)の鉄道分野規格の対応検討を行う鉄道車両の騒音測定規格検討WGの委員および主査として、長年にわたり国内規格審議を牽引し、規格原案の策定に尽力した。また、国際エキスパートとしてCEN(欧州標準化委員会)/TC 256(鉄道分野)/WG 3(騒音排出)の審議に加わり、車内騒音測定法ISO 3381の発行、また、車外騒音測定法ISO 3095におけるコンクリート高架橋での鉄道車両に関する日本の測定法の国際規格案(DIS)への記載など、長年にわたる両規格に対する国内鉄道事業者および車両メーカーの課題および疑義解消に大きく貢献した。
|
| 高橋 弘隆 氏 |
株式会社日立製作所 |
長年にわたり、地上電力設備に関係する規格化活動に参加し、国内作業部会の委員や主査、また、国際エキスパートとして規格審議、策定に貢献した。IEC 62924(地上電力貯蔵システム)他の活動が評価され、2014年度に標準化活動奨励者表彰を受賞した。その後、同分野の国際標準に係わる国内委員会に参画し、日本提案の交流電力補償装置の規格原案作成を進めるほか、2020年度からは鉄道国際規格センターの電力部門別連絡会座長を務めるなど、わが国の鉄道技術の標準に関する対応方針の策定に貢献した。
|
| 藤井 秀宜 氏 |
元:三菱プレシジション株式会社 |
長年にわたり、ISO/TC 269/SC 3(オペレーションとサービス)における日本提案の運転シミュレータの国際規格審議で、国内組織発足時から国内主査を務め、国内の意見を調整してまとめてきた。同氏は、国内規格等がない本件の作業原案ISO WD 23019(運転士訓練用運転シミュレーター)を執筆し、その後の委員会原案(CD)および国際規格案(DIS)の登録に貢献した。また、この国際規格に関する国際エキスパートを務め、規格審議の議論を主導して各国の合意を獲得し、日本提案の受諾に繋げるなど、わが国の運転シミュレータ技術の国際規格化の審議に多大に貢献した。
|
| 南 智之 氏 |
東海旅客鉄道株式会社 |
海外展開において日本の新幹線をデファクト化すべく、外国の制度変更に尽力し、国際標準化におけるこれまでにない先駆的な取り組みを行った。具体的には、延べ12年にわたり、安全基準を策定するRSAC(米国連邦鉄道局鉄道安全性諮問委員会)内の高速鉄道の安全基準を議論するタスクフォースにおいて、日本の新幹線技術を包含する安全基準(連邦規則)策定に貢献する一方、米国において新幹線の安全基準の採用を認めるRPA(特定のプロジェクトに適用される連邦規則作成の枠組み)においてFRA(米国連邦鉄道局)に協力し、米国でも初めてとなるRPAを活用した連邦規則の策定と施行に貢献した。
|
| 村﨑 研史 氏 |
東日本旅客鉄道株式会社 |
ISO/TC 269/SC 3/WG 3(輸送計画)のエキスパートおよび国内委員を務め、運転時分計算の規格審議に貢献した。また、ROQC(欧州鉄道事業者が、欧州鉄道産業連盟の鉄道品質マネジメントシステム(RQMS)の認証スキームに関する団体標準への影響力を行使するために設立した団体)の委員、2021年にはISO/TC 269/WG 5(RQMS)の国内委員及び国際エキスパートを務め、その規格審議において欧州の鉄道事業者と連携し、欧州メーカー提案の標準化に対して鉄道事業者としてグローバルな対応に取り組み、日本の主張を反映させることに貢献した。
|
| 森貞 晃 氏 |
日本信号株式会社 |
長年にわたり、IEC/TC 9/PT 62773(列車制御用無線要求決定手順)、IEC/TC 9/AHG 9(RAMS規格における追補)等の国際エキスパートとして規格審議および策定に貢献するとともに国際主査の補佐を務めた。また、IEC/TC 9/WG 45(自動運転都市内軌道旅客輸送システム)、IEC/TC 9/MT 62278(RAMS)、IEC/TC 9/MT 62425(信号用安全関連電子システム)、IEC/TC 9/MT 62427(車両と列車検知システムの両立性)、IEC/TC 9/AHG 27(中立セクション)、ISO/TC 269/SC 3/AHG 2(列車在線検知の原則)等の多数の規格審議の国際エキスパートも務めて、わが国鉄道技術の国際標準化に貢献した。
|
|
|
|
|
令和3年度 標準化活動奨励者表彰 受賞者 (50音順)
|
|
| 受賞者 |
所属 |
受賞理由 |
| 熊澤 一将 氏 |
公益財団法人鉄道総合技術研究所 |
延べ6年間にわたり、運転曲線作成システムや輸送計画のための運転時分計算方法の作業部会等に参加して、国内審議活動に貢献した。特に、作業原案ISO WD 24675(輸送計画のための運転時分計算 - 要求事項)の技術的内容の執筆に中心的な役割を果たした。また、ISO/TC 269/SC 3/WG 3(輸送計画)の国際エキスパートを務め、輸送計画の国際標準化の分野を中心に、今後とも一層の貢献が期待される。
|
| 齊藤 雄介 氏 |
東日本旅客鉄道株式会社 |
延べ3年間にわたり、輸送計画のための運転時分計算方法の作業部会に参加し、資料のとりまとめを行うなど国内委員会の活動に貢献した。また、ISO/TC 269/SC 3/WG 3(輸送計画)の国際エキスパートを務め、各国エキスパートと議論を行い国際規格案ISO/DIS 24675(輸送計画のための運転時分計算 - 要求事項)作成に寄与するなど、輸送計画の国際標準化の分野を中心に、今後とも一層の貢献が期待される。
|
| 清水 俊匡 氏 |
東海旅客鉄道株式会社 |
延べ5年にわたり、新幹線で導入事例が多い日本提案による交流電力補償装置のほか、交流電力変換装置、き電シミュレータ、地上電力貯蔵システムに関する国内作業部会の委員を務め、国内審議活動に取り組んでおり、電力技術の国際標準化の分野を中心に今後とも一層の貢献が期待される。
|
| 宮崎 祐丞 氏 |
西日本旅客鉄道株式会社 |
延べ5年にわたり、軌道品質評価作業部会の委員等を準備会段階から継続して務め、国内審議活動に貢献した。また、ISO/TC 269/SC 1/WG 2(軌道品質評価)の国際エキスパートを務め、日本の軌道管理手法が国際規格案ISO/DIS 23054-1(軌道品質評価 - 第1部:軌道線形の特性と軌道品質評価)に記載されるように尽力し、軌道技術の国際標準化の分野を中心に今後とも一層の貢献が期待される。
|
| 米盛 逸人 氏 |
株式会社総合車両製作所 |
延べ3年にわたり、ISO/TC 269/WG 5(鉄道品質マネジメントシステム(RQMS))およびISO/TC 269/AHG 18(RQMSの適合性評価)の国際エキスパートを務め、RQMSの規格審議に貢献した。また、ISO/TC 269/SC 2/WG 7(脱線検知システム)の国際エキスパートならびに脱線検知装置作業部会および車両火災防護作業部会の委員を務め、車両技術の国際標準化の分野を中心に、今後とも一層の貢献が期待される。
|
|
|
| ISO: |
International Organization for Standardization(国際標準化機構)の略。電気・電子分野以外の国際規格を策定している。
|
|
| ISO/TC 269: |
Technical Committee 269の略。ISOの鉄道分野に関する専門委員会。
|
|
| ISO/TC 43/SC 1: |
Sub Committee 1の略。ISOの騒音測定法に関する分科委員会。
|
|
| IEC: |
International Electrotechnical Commission(国際電気標準会議)の略。電気・電子分野の国際規格を策定している。 |
|
| IEC/TC 9: |
Technical Committee 9の略。IECの鉄道用電気設備とシステムに関する専門委員会。 |
|
| FRA: |
Federal Railroad Administrationの略。米国連邦鉄道局。
|
|
| RSAC: |
Railroad Safety Advisory Committeeの略。FRAの鉄道安全性諮問委員会。
|
|
| RPA: |
Rule of Particular Applicabilityの略。特定のプロジェクトに適用される連邦規則作成の枠組み。
|
|
| ROQC: |
Railway Operator Quality Councilの略。欧州鉄道事業者が、欧州鉄道産業連盟の鉄道品質マネジメントシステム(RQMS)の認証スキームに関する団体標準への影響力を行使するために設立した団体。
|
|
| RQMS: |
Railway Quality Management Systemの略。鉄道品質マネジメントシステム。
|
|
|
|
|
|
|
|